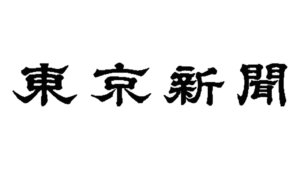【相談】子の貧富の差激しい どう接する60代男性・学童支援員・千葉県 認定NPO法人キッズドア理事長 渡辺由美子さん
相談
学童保育で支援員をしていますが、子どもたちの貧富の差が激しいと感じます。週3回の塾、プールなどに行っている子がいます。嫌々通っているケースもあります。長期休みになると、海外や国内の旅行に当然のように行く子もいます。かたや、習い事に通いたくても、家庭の事情で行けない子もいます。お金がなかったり、シングルマザーだったり……。そういった子の中には週5日、学童が閉まる寸前までいる子もいます。
気をつかってこちらからは塾や旅行の話題は、子どもたちの前ではなるべくしないようにしています。子どもたちにどう接すれば良いでしょうか。
広がる「体験格差」 人生談で興味の扉を
回答
相談者さんの実感は正しいと思います。子どものいる世帯間の格差は広がっています。国民生活基礎調査をもとに、子どものいる世帯の所得を1990年と2021年で比較してみました。1990年に最も多かった層は500万〜550万円。2021年は1200万〜1500万円が最多の層です。1990年と比べ、共働き世帯が増えたことが背景にあります。1人500万円の所得でも「2馬力」なら計1000万円。そのため、ひとり親家庭などの「1馬力」かつ、所得が低い世帯との差は広がっているのです。さらに、2021年の子どものいる世帯の所得の中央値は710万円で、全 世帯の中央値(423万円)より287万円も多い。子育て世帯に高収入の方が増えているともいえます。家計に余裕がある家庭は、子どもを塾に行かせ、夏休みは海外を含む素敵な旅行に行く……。そういったこともできるでしょう。
高所得の人がどんどん教育に投資するので、その差は開いていきます。
見えにくいだけで、日本ではお米の値段が上がれば買えない家庭があります。そういった家庭は夏休みに子どもをどこにも連れて行ってあげられません。でも、一日中子どもが家にいるとエアコン代がかさみます。そのため、開所時間いっぱい学童などにいてもらうことになります。
キッズドアが24年、困窮する家庭を対象に、夏休みに予定しているアクティビティー(体験活動)についてアンケートをしたところ、「特になし」が52%で最多でした。
「体験格差」という言葉がありますが、体験は子どもたちの成長に重要なのです。普段の勉強に向かうモチベーションにもなります。
コロナ禍を経て、宿泊学習など学校教育でできる体験活動が縮小しているとも聞きます。学校の代わりに様々な体験を子どもに提供できる家庭は良いですが、そうでない家庭との差は広がってしまいます。
相談者さんのように、子どもに関わる仕事をする方をはじめ、子どもがいる家庭の近所に住む方にもできることがあります。ぜひ、ご自身の話を子どもにしてあげてください。
高校や大学で何を勉強したのか、どんな会社に勤め、どんな仕事をしてきたのか──。ご自身の体験でかまいません。それも子どもにとっては貴重な「体験」になります。困窮する母子家庭の子どもの中には、会社で働くイメージがない子もいます。話を聞くことで、子どもの興味の扉が開くことがあるからです。(構成・小林直子)
渡辺由美子 わたなべ・ゆみこ
内閣府の「子供の貧困対策に関する有識者会議」構成員。2000年から1年間、家族で英国に住み、「社会全体で子どもを育てる」ことを体験し、07年にキッズドアを設立。千葉大学工学部出身。
2025年10月14日(火)朝日新聞朝刊教育面
白黒で一部カラー.png)