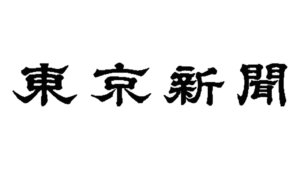2025/09/14 朝日新聞朝刊くらし面 坊美生子の女性のマネーデザイン「老後の貧困リスク、消費意識の差との関係は」
今回は世代による消費の意識や習慣の違いと、老後の貧困リスクについて考えます。女性は人生終盤に「おひとりさま」になる可能性が高く、今は夫婦でも、夫の死後は年金の他に収入や資産がなければ貧困リスクが高まる。これまでにそう説明しましたが、社会の関心はいま一つ高まっていないように思います。高齢女性の貧困リスクが表面化しづらい理由として、おひとりさまが一部の未婚や離別の女性だけの問題のように思われがちであると以前に述べました。加えて、消費への意識や習慣の違いも関係するのではないかと思います。
現在の後期高齢者は物が足りなかった戦後に育ち、下の世代に比べると物を大切に使うなど、お金をかけずに生活する力があるように感じます。低い年金額などのデータが示すほどには、生活に困っていないのかもしれません。その下の世代はどうでしょうか。例えば、今の50代後半から60歳頃までのバブル世代の方は「ブランド好き」「ぜいたく好き」などと評されることがあります。老後に単身となり収入が減った後、戦後世代と同様につつましい暮らしをして、同じぐらいの生活満足度を得られるでしょうか。総務省「全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)=から、バブル期だった1989年の30歳未満の単身女性の「被服及び履物」の支出額を、その5年前や後の時代の30歳未満と比べました。物価変動の影響を加味しても最も高く、バブル期の若者は衣服にお金をかけた世代だと言えます。もちろんこれは若い頃の消費行動で、シニアになった現在の支出ではありません。ただ、一度身に付いた意識や習慣は少なからずその後にも影響するでしょう。給与や年金については世代間の差が学術的にも研究されていますが、仮に収入が同じであっても、消費への意識や習慣の差によって生活満足度に差が生じる可能性はあるのではないでしょうか。つまり、バブル世代の人は生活困窮に対する感覚が今の高齢者世代より敏感になり、高齢女性の貧困リスクの課題が今より切実になる可能性があると考えています。その後は雇用環境に恵まれなかった就職氷河期世代が高齢期を迎えます。高齢女性の貧困リスクの課題はさらにクローズアップされるように思います。
ぼう・みおこ 読売新聞記者を経て、2017年にニッセイ基礎研究所に入社。生活研究部准主任研究員として、中高年女性の雇用と暮らし、高齢者が使いやすい移動サービス、高齢社会のあり方などを研究している。
◆第2・第4日曜日に掲載します。
白黒で一部カラー.png)