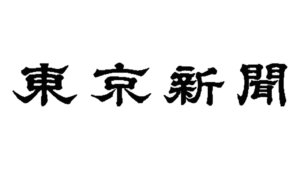不登校、ではないけれど4⃣ 勝者像とズレる自分 教室は苦手だが
職員室・塾・・・「いてもいい場所」見つけ
東京都の高校3年の男子生徒は、週数回、職員室に登校している。課題をもらい、半個室の談話スペースで自習する。「ここは騒がしくないし、拘束されていない感じがする」
学校は難関の中高一貫校。中学受験の勝者だとして、周囲から称賛と期待が集まった。
だが、入学直後からつまずいた。コロナ禍による一斉休校で勉強のリズムを失い、部活動に入るタイミングも逸した。親友と呼べるような人はおらず、何となく疎外感を感じ続けた。
中2の後半からは起立性調節障害の症状にも悩まされた。朝起きるのもつらい。自慢だった学力も自信はない。学校に行っても机で気絶しているかのように過ごした。
学校に理解があり、高校には進めたが、中3の3学期からほぼ不登校状態。「君ってすごいね。もっとできるよね」——中学受験の時に周囲から期待された像が、現実とどんどんずれていった。
高1の春、小学校時代の友達が通う高校の文化祭に誘われた。キラキラした青春と自分の状況を比べて耐えきれず、すぐに帰った。「何か違えば自分もこちら側にいたのかな」家にいる間はずっとゲームをして、〇にたいという思いからひたすら逃げていた。
スマートフォンを触れば、SNSから同年代の「キラキラ」が飛び出してくる。高校生にもなればスポーツや芸術などで活躍する同世代も出てきて、ニュースになる。それを見るだけで苦しかった。「自分は何も積み上げてないな」
高2になると、少しずつ起立性調節障害の症状がおさまり、勉強にも取り組めるように。
ただ教室は今も苦手だ。
そのうち、職員室に課題をもらいに行き、そのまま談話スペースでこなすことが増えた。週に数回登校し、数時間かけて問題を解く。先生が用意してくれた紙に取り組んだり、今後の目標などを書き、少しずつ自信を積み上げる。
さらに受験に向けて、不登校生らの大学進学をサポートする「河合塾コスモ」にも通う。以前は周囲の期待に応えられず、自分の居場所がわからなくなったが、今は学校の内外に「いてもいい場所」が複数あることが重要だと感じている。
不登校ではないけれど、100点でもない。でも、それでもいいと納得できる。そんな自分自身の解釈を、ちょっとずつ見つけられた気がする。(狩野浩平)
通えていても「サイン」に気づいて
芳川玲子・星槎大学大学院教授(臨床心理学)の話
学校に通ってはいるけど、「不登校と同じような課題を抱えている子どもたちは多いと思います」。
不登校は、学校に通うか通わないかという二択ではなく、不調を訴えたり遅刻・早退しながら通い続けるといったグラデーションがあります。そうした子は文部科学省の不登校の定義には当てはまりにくく、不登校調査の結果にも表れてきません。
本格的に不登校になってしまうと、支援するのはとても大変です。学校に通えているかどうかにとらわれず、早期のサインに気づき、放置しないことが大切です。
文科省は、自分の教室に入りにくい子にとって学校内の居場所となり得る「校内教育支援センター」の設置を促進していますが、その質には大きなばらつきがあります。利用者が増えれば、不登校の数は減るでしょうが、それで問題解決とは言い切れません。
重要なのは、校内居場所を利用する子たちが通常の教室も安心な場だと感じられることです。そのためには教室の中の学習スタイルや評価のあり方をもっと多様にする必要があります。
=おわり
2025年10月12日(日)朝日新聞朝刊教育面
白黒で一部カラー.png)