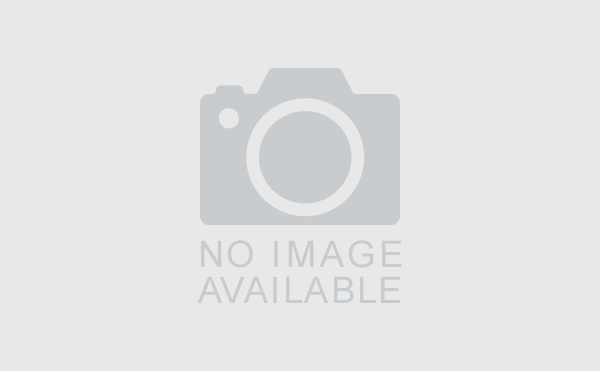2025/09/04 東京新聞朝刊暮らし面「誰もが安心な『優しい住』を」国が資金助成 先進事例を後押し
高齢者や障害者、子育て世代らに配慮した住まいが各地に広がっている。安否確認や生活相談を提供するサービス付き濶齢者向け住宅(サ高住)を団地内に設けたり、車いす利用者らが災害時に避難できる設備を備えたり。誰もが安心してむらせる住環災を整えようと、国も資金面などで後押しする。(古根村進然)
・団地内に開設住民とも交流
サ高住とともに、障害者が暮らすグループホーム(GH)を備える名古屋市北区の「ミドウムおおぞね」。愛知県住宅供給公社が所有する築約50年の団地内の70戸を、地元の社会福祉法人「共生福祉会」が借りて改修し、2023年5月に開設した。サ高住の家賃は月約6万円で、安否確認などのサービス費が1人2万円かかる。GHの家賃は1人3万円で、朝夕食代などとして4万8千円がかかる。現在はほぼ満室だ。団地には誰でも利用できる食堂や交流スペースもあり、入居者は団地の住人らと気軽に触れあえ、施設暮らしとは感じにくい。昨年10月からサ高住に入る前原光江さん(83)は「外出制限もなく、普通の生活を送っている。隔月の懇談会で友達もでき、安心して過ごせる」と満足げだ。この方式だと障害者と高齢の親が近居でき、「親亡き後」の不安の軽減にもっながる。「親がサ高住に入り、障害のある子がGHで暮らせ、家賃も割安。親は最期まで安心できる」と、統括する西尾弘之さん(71)は言う。ミドゥムおおぞねは、建物の老朽化や空き室の増加といった団地の課題を逆手にとり、多世代が安心して暮らせる場に再生させた。住宅の改修などに約3憶6千万円かかったが、国土交通省の「住まい環境モデル事業」に選ばれ、約2億4千万円が助成された。この事業は、地域の課題解決などにつながる取り組みを支援しようと、19年度から開始。学識経験者による評価委員会の審議を経て選定された場合、改修工事費などに3憶円を上限に助成される。24年度までに各地の100件が選ばれた。
・スロープ設け車いすも安心
18年の西日本豪雨で高齢者ら50人超が犠牲となった岡山梨念敷市真備町に、20年6月にオープンした2階建ての「避難機能付き共同住宅」もその一つ。駐車場
から2階まで傾斜の緩い約30メートルのスロープがあり、災害時に上層階へ逃げることが難しい車いす利用者らが使える。地元で介護事業所などを運営する津田由起子さん(61)が被災した賃貸住宅を改修した。現在は、車いす利用者や高齢者ら7世帯が住む。2階の一室は住民らの交流や避難時に使えるスペースとし、食料や蓄電池なども備蓄。津田さんは「災害弱者らが不安なく暮らせる楊所を提供したい」と話す。神戸市にある4階建ての共同住宅「六甲ウィメンズハウス」は、経済的困窮などで住宅取得が難しいシングルマザーや女子大生らが対象。地元の認定NPO法人「女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ」と公益財団法人「神戸学生青年センター」が、生活協同組合コープこうべから旧女子寮の無償貸与を受けて改修し、昨年6月に運営を始めた。1人部屋から子ども数人と暮らせる部屋まで計40室がそろう。現在は24世帯が入居。家賃は2万~5万円台。保証人、敷金礼金は不要だ。入居期限は原則3年。就労支援も受けられ、NPOの代表理事の正井礼子さん(76)は「入居者が自分らしさを取り戻せるよう手助けしたい」と話す。
・終末期の人か自宅のように
滋賀県内で病院や介護事業所などを営む公益財団法人「近江兄弟社」(同虹近江八幡市)は、旧病棟を改修してがんなどを患う人が最期までむらせる「ナーシングホームヴォーリズ希望館」を26年4月に開く計画だ。専門医の訪問診療を受けられ、看護師や介護士が常駐。20室あり、家賃と食事代で月9万5千円。副理事長の沢谷久枝さんは「外出や面会は自由。家族と食事を楽しめ、自分の家のように過ごせる」と話す。モデル事業の評価委口長を務める東京通信大の高橋紘士名誉教授(福祉政策論)は「空き家や廃校を活用したり、産学官連携したりする事業もあり、各地への広範な波及効果が見込まれる」と説明。「今
後も地域の創意工夫を生かして長寿社会に対応し、幅広い世代の多様な人たちが生きがいを感じられる住まいが求められる」と指摘する。
白黒で一部カラー.png)